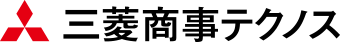数々のハードルを乗り越え
海外の工場の稼働率をアップせよ!
海外へ事業展開する製造業のお客さまに対して、当本部では生産設備や周辺機器の調達・販売、アフターケアなどのサービスを主に提供してきました。それらに加え、現場管理に関するご相談などにも応えるべく、新たなチャレンジがスタートしています。社内のスペシャリスト人材を活用した、海外の工場におけるコンサルタント業務の事例をご紹介します。
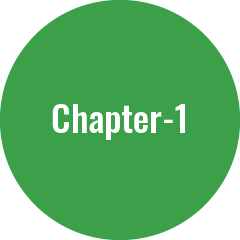
製造業を知り尽くした
スペシャリストを現地に派遣
2023年8月、お取引のあったインドネシアの日系自動車部品製造業のお客さまから、「工場の稼働率を上げたい」というご相談が寄せられました。機械商社であるわが社にとっては、ほとんど経験したことがないミッションです。ただ、折よく大手自動車メーカーのメンテナンス経験者の採用を検討していた事から、早速そのエンジニアをお客さまの工場に派遣し、TPM活動※に参加しました。TPM活動を始めてみると、さまざまなデータは揃っているものの、それらが活かしきれていないという印象を得ました。現場を繰り返し観察して浮き上がってきた改善項目をレポートにまとめて提出しました。これだけでも一応の成果は達成されましたが、当プロジェクトはこれで終了ではありません。むしろここからがスタートです。これら数々の課題を一つずつ改善するため、わが社のチャレンジが始まりました。
改善すべき課題の例として、日常点検の形骸化がありました。20ほどの項目を始業前の5分間で点検していました。これでは形だけのチェックになるのも無理ありません。担当者の負担を減らすために点検項目を必要最小限に抑え、稼働後でも可能なものはリーダー職などに分担。できないことはできるように仕組みを変えるというのがTPM活動の基本です。
機械にたまる切削屑の処理も、製品の品質低下や設備故障にもつながる課題の一つでした。担当作業者がその都度掃除すれば済みますが、その時間も生産活動においてはロスになります。そこで機械の一部にゴムのカバーをつけ、屑がたまらないようにしました。カバーの形状もいろいろ試して、効果的なものを選び出しました。事後処理よりも事前に対処。これもまたポイントの一つです。
これらはほんの一例で、その他にも工場内のムリ・ムラ・ムダを見つけては、一つずつ解決していくという地道な作業が繰り返されました。
※TPM(Total Productive Maintenance)活動:製造現場の工場・設備で発生するあらゆるロスを未然に防止することを目的とした仕組みや管理体制を作り、生産性の効率化を図る活動

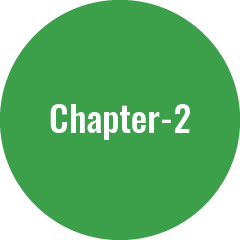
社員のやる気向上を促す環境を
一緒につくり上げる
作業の改善を進める上で真っ先に課題となったのが、コミュニケーションとリーダーシップの不足でした。そこで課題を指摘して改善「させる」のではなく、現地の社員とディスカッションを重ね、一緒にアイデアを導き出すことに奔走しました。現場で社員と一緒に清掃作業もしながら意見を引き出し、試行錯誤を繰り返していきました。
工場の特定の一ラインをテストケースとして改善活動を行った結果、半年間で平均設備総合稼働率が68.54%から78.82%へと10%以上も向上しました。結果が現れれば現場のモチベーションは上がり、コミュニケーションも密になります。ミーティングへの参加者も次第に増えていきました。
そして2024年8月からは第2フェーズに突入しました。2本のモデルラインを設置し、リーダー職を明確に任命。それぞれのリーダーにはデータの収集や分析・解析まで責任を持って担当してもらいました。毎月フォロー、レビューをすることで、改善度合いは数字で確認されます。それによりリーダーは達成感を獲得し、改善の必要性が作業者全体に広がっていきます。各人のモチベーション向上は、TPM活動にとって非常に重要なポイントです。
第2フェーズのゴールは12月末。それまでに両ラインの設備総合稼働率を78%に上げることが目下の目標です。その目標値は間違いなくクリアできそうです。

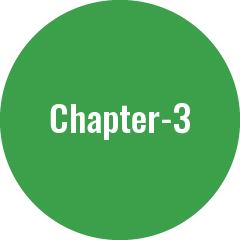
文化・習慣・言語などの
壁を乗り越えてお客さまの要望を達成
成果が着実に上がっているとはいえ、700人もの社員が働く大規模な工場全体においては、現在のところ2割程度の範囲に過ぎません。これから着手すべきこともまだまだあり、現状は道半ばといったところです。
しかし、モデルラインと他のラインを比べると、生産設備のきれいさ、作業効率の良さなどは、傍目にもはっきりと違いが見て取れます。他の社員が成功体験を間近に目にすることと、けん引する人材の成長・増加により、2025年以降に予定されている他のラインへの拡大は、これまでの何倍もの速さで進むと思われます。最終目標である工場全体の稼働率向上も、それほど遠いことではないでしょう。
今後はこうしたTPM活動の活性化と合わせて、組織面の提案もしながらミッションを進め、将来的にはIoTシステムの導入やカーボンニュートラルへの対応などについても、ご相談に対応していく予定です。
海外の工場におけるこうした活動には、国内とは違った難しさが数多くあります。文化や習慣、言語などさまざまな壁が存在し、それらをしっかり把握した上での活動が必要とされます。海外本部では、こうしたハードルも含め、海外における現場管理・保全業務に関するスペシャリストを育成し、同様のケースに備えています。当プロジェクトの経験を基に、各国の製造業の現場からのさまざまな相談に対応できるよう準備を進めています。